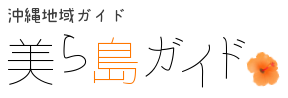沖縄の独自野菜
沖縄は日本の最南端に位置する地域であり、古い時代から中国や台湾と交流があったために、その国の影響を受けた文化も発達しており、日本の他の地域と違う独自の文化を形成しています。
また沖縄という特有の気候も独自性があり、1年中気温が高い地域でありながら、夏になると台風が発生し、必ずと言っていいほど台風が直撃する地域です。
そのような地域のために、沖縄の野菜も独自のものが多く、暑さに強く風にも強い野菜が多いのです。
そしてこのような独自の野菜を使った、沖縄特有の料理も数多くあります。
こうした料理は家庭料理としてばかりでなく、料理屋などでも出されるメニューのため、沖縄に旅行に行けば沖縄独自の料理を楽しむことも可能です。
また最近は通販でも沖縄の野菜を取り寄せて味わうことも出来ます。
沖縄の代表的な野菜
沖縄の代表的な野菜はいくつかありますので、ここでご紹介します。
・ゴーヤー
沖縄の野菜と言えばゴーヤーを思い浮かべる人も多いでしょう。
他の地域ではニガウリと言われることが多い野菜であり、沖縄にはいくつかの品種が存在します。キュウリのように緑で長細い形状であり、外側にはごつごつした凹凸があります。
沖縄の野菜と言えばゴーヤーを思い浮かべる人も多いでしょう。
他の地域ではニガウリと言われることが多い野菜であり、沖縄にはいくつかの品種が存在します。キュウリのように緑で長細い形状であり、外側にはごつごつした凹凸があります。
この野菜を使った料理と言えばゴーヤーチャンプルが有名ですが、その他にもサラダや天ぷらにもなり、ゴーヤーチップスや飲み物にもなります。
ちなみに沖縄にはゴーヤーマンというキャラクターがいます。
・ナーベラー
ヘチマのことであり、沖縄ではナーベラーと言います。
若い実は炒め物や汁ものなどに使われ、化粧品の原料になったり、タワシとして利用されたりと、その用途はいくつもあります。長いと1m近くになる場合もありますが、最近は30cmぐらいのが主流です。
ヘチマのことであり、沖縄ではナーベラーと言います。
若い実は炒め物や汁ものなどに使われ、化粧品の原料になったり、タワシとして利用されたりと、その用途はいくつもあります。長いと1m近くになる場合もありますが、最近は30cmぐらいのが主流です。
・チデークニー
黄色い色をした細長い人参です。
一般的に見られる赤っぽい人参は西洋からきたものですが、この人参は中国から渡ってきました。沖縄では島ニンジンという名前でも呼ばれており、栽培されています。
ちなみに沖縄でいう島という言葉は沖縄のという意味があります。
黄色い色をした細長い人参です。
一般的に見られる赤っぽい人参は西洋からきたものですが、この人参は中国から渡ってきました。沖縄では島ニンジンという名前でも呼ばれており、栽培されています。
ちなみに沖縄でいう島という言葉は沖縄のという意味があります。
・ダッチョー
ラッキョウの事であり、一般的なラッキョウよりは小さめです。
香りや辛みが強く、天ぷらや漬け物などになります。沖縄では島ラッキョウと言われており、沖縄の人にとってはなくてはならない食材です。
天ぷらなどにするときは小さめのものを、漬け物にするときは大きめのものを使うと良いです。
ラッキョウの事であり、一般的なラッキョウよりは小さめです。
香りや辛みが強く、天ぷらや漬け物などになります。沖縄では島ラッキョウと言われており、沖縄の人にとってはなくてはならない食材です。
天ぷらなどにするときは小さめのものを、漬け物にするときは大きめのものを使うと良いです。
・ターンム
サトイモの一種であり水田で栽培されます。
熱帯地方が原産であり、沖縄では本島中部で栽培されます。汁ものや炊き込みご飯や天ぷらや煮物など、通常のサトイモと同じように料理して食べられます。
煮込むととろみがでて、茹でたものも流通しています。
サトイモの一種であり水田で栽培されます。
熱帯地方が原産であり、沖縄では本島中部で栽培されます。汁ものや炊き込みご飯や天ぷらや煮物など、通常のサトイモと同じように料理して食べられます。
煮込むととろみがでて、茹でたものも流通しています。
味噌汁にするような事も多く、豚肉や野菜と一緒に味噌汁の具材として使われます。