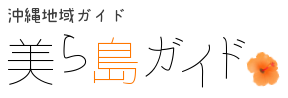やちむんとは
やちむんとは、沖縄の言葉では焼き物の事を言い、1600年頃にまだ沖縄が琉球王国と言われていた時代、中国やタイから陶磁器が持ち込まれ、同時に焼き物の技術が出来上がっていき、やちむんという沖縄独自の焼き物が誕生しました。
壺として作られる事が多いですが、それ以外にも食器など生活用品のやちむんもあり、沖縄で愛用されており、若い女性を中心に人気があり、県外でも注目されている焼き物です。
やちむんの原点は1616年に薩摩藩から琉球に焼き物の技術指導に訪れたのが始まりといわれており、1682年には焼き物産業の復興を目指しました。
そして明治以降になると泡盛の輸出が増えると同時に、やちむんの壺の生産も増えて活気づいていきます。
しかし琉球王国が沖縄になると県外から安価な焼き物が入ってきて、やちむんは衰退してしまい、現在にいたりまた少し注目を浴びています。
現在のやちむん
現在のやちむんは2種類あり、荒焼のアラヤチと上焼のジョーヤチの2種類あります。
アラヤチは1600年代から作られているやちむんであり、壺など大型の物が多く釉薬を使わずに焼き土質感が残ります。
ジョーヤチを使い装飾し、食器や酒器などが作られ、今のやちむんの主流となっています。
やちむんを焼くときはガス釜と登り窯のどちらかを使いますが、ガス釜だと温度が安定し綺麗に焼け、登り窯だと色や艶のムラが出ますが、それが味になって良い質感を出します。
現在は読谷村がやちむんの聖地と言われており、多くの観光客が訪れるところとなっています。
また1600年代から釜場としてやちむんが作られているのが壺屋やちむん通りであり、こちらも観光客の多い場所です。
どちらもやちむんを語る上ではなくてはならない場所であり、壺屋は昔ながらの伝統のある場所であり、読谷村は1970年代に焼き物作りが始まったばかりの若い場所ですが、パワーのあるところでもあり、新しいやちむんが次々と登場しています。
やちむんの作家もおり、有名なところでは松田米司氏であり、イギリスで個展を開くなどその実力を海外で発揮しています。
若手では石倉一人氏がおり、瀬戸で修業したあと、県外の技術を取り入れて新しいやちむんを作っています。
もちろんやちむんは観光として訪れても購入する事が出来、壺屋に行けば多くのお店が並んでおり色々な種類のやちむんを見ることが出来、読谷は工房が多数ありますので、やちむんを焼いている様子なども見ることが出来ます。
やちむんの何を見たいかでどちらに行くか決めると良いでしょう。