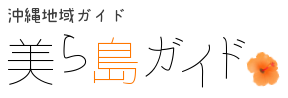第二尚氏の陵墓…じゃあ第二尚氏とは?
1879年、沖縄に沖縄県が設置されました。
それまでは琉球王朝が存在し、王家が国を支配していた状況でした。
江戸時代には薩摩藩による実質上の支配を受けていた面もありますが、沖縄県が設置されるまで沖縄は独立した国だったわけです。
そのため、本土とはかなり異なる歴史や伝統・信仰を持っています。
第二尚氏は、その1879年まで存在していた琉球王朝の王家の一族の名前です。
初代は1469年に即位した尚円王、以後約410年間にわたって琉球王国として沖縄を支配していました。
なお、沖縄県設置後にこの一族は日本の華族として扱われています。
その子孫は現在でも健在で、1992年に当時の当主が沖縄県に寄贈する形で県の史跡となった経緯もあります。
「玉陵(たまうどぅん)」とは、そんな第二尚氏の歴代の王が葬られ、眠っている陵墓なのです。
まさに独自の歴史を重ねてきた沖縄を象徴するスポットと言えるでしょう。
玉陵ってどんな場所?
作られたのは三代目の王、尚真王(1477-1527年)の時代と考えられており、全体は大きく中室、東室、西室の3つの建造物に分けることができます。
さらに出入り口にあたる前門、後門、琉球王朝時代にこの地の被葬者になるための条件が書かれた「玉陵の碑文」なども見どころです。
施設そのものが数百年もの歴史を経ているほか、石に彫られた雌雄の獅子像や中庭には珊瑚の破片が敷き詰められているなど、印象的な特徴を持ち合わせています。
現代の私たち日本人、とりわけ本土の方たちにとっては異国情緒を感じさせる魅力を持っていると言えるでしょう。
現在では観光スポットとしての面が強く、有料の施設となっています。
入り口にあたる「奉円館」という場所で入場料金を支払って入場します。
ここには「玉陵資料館」もあるので、まずここで基本的な知識を学んでおくと鑑賞がより楽しく充実したものになるでしょう。
玉陵の歴史
このように古い歴史を持つ場所ですが、太平洋戦争の沖縄戦において大きなダメージを受けました。
日本軍の総司令部がこの施設の近くに置かれていたため、激しい砲撃に晒されることになってしまったからです。
そのため、現在見ることができる部分の多くは戦後になって再建されたものとなっています。
琉球王朝の歴史に触れる場所であるとともに、沖縄戦の激しさ、悲惨さを垣間見ることができる場所とも言えるでしょう。
2000年に「琉球王国のグスク及び関連遺産群」が世界遺産に登録されましたが、そのなかにこの玉陵も含まれました。
つまりれっきとした世界遺産のスポットとなるわけで、ほかにも全体が国の史跡でもあります。
さらに一部の墓室・建造物が国宝に認定されているほか、先述した石彫りの獅子像が県の有形文化財に指定されています。