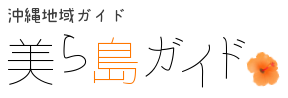沖縄最大の聖地にしてパワースポット
斎場御嶽は、「せーふぁうたき」と読みます。
本土とは異なる独自の歴史と伝統・信仰を受け継いできた沖縄にとってもっとも重要な聖地であり、また現代を生きる私たちに神秘的な印象を与えてくれるパワースポットでもあります。
この斎場御嶽は、第二尚氏と呼ばれる琉球王朝の時代に作られた聖地です。
1429年から1879年まで続いたこの琉球王朝においてもっとも初期に作られた聖地であり、また琉球の祖神とされるアマミキヨが国を作り始めたときに最初に作った7つの御嶽のひとつでもあります。
神聖な神託の場であるとともに「男子禁制」の場でもあった地
沖縄では「ユタ」や「ノロ」と呼ばれる女性の巫女が信仰において非常に重要な役割を担っていますが、琉球王朝においては「聞得大君」と呼ばれる巫女(神女)がその最高峰の地位にありました。
斎場御嶽は、そんな聞得大君が創造神と契りを交わすと言われる「お新下り」と呼ばれる重要な儀式が行われる場所でした。
聞得大君が交代する際には、この儀式が就任の儀式として行われました。
また、巫女が神から神託を受ける場でもありました。
そんな神聖な場である斎場御嶽の最大の特徴とも言えるのが、かつて「男子禁制」の場であったという点です。
本土では修験道をはじめとして女人禁制の歴史を持つ聖地が各地に見られますが、沖縄でもっとも重要な聖地は男人禁制だったのです。
現在では男性でも立ち入ることができますが、琉球王朝時代では国王でさえ、この地を訪れるときには入り口にあたる「御門口(うじょうくち)」から先は女装し「女になった」うえで足を踏み入れる必要があったと言われています。
自然とともにある神秘の空間を感じ、味わう場所
現在この地を訪れる私たちにとって大きな特徴となっているのが、神殿などの神を祀ったり祈るための特別な建築物がない点です。
巨石・巨岩、あるいは樹木といった自然そのものが信仰の対象となる、アニミズム的な世界観がそこには広がっています。
沖縄といえば海に代表される開放的な雰囲気を連想される方が多いかもしれませんが、斎場御嶽はそんなイメージとはちょっと違った神秘的な世界を味わうことができます。
なお、現在でもかつて行われていた信仰の行事を伝える「東御廻り(あがりうまーい)」という行事が行われるなど、沖縄の信仰と歴史を今に伝える場としての役割も失われていません。
沖縄の歴史や伝統に興味がある方なら、真っ先に訪れたいスポットの一つとなるでしょう。
また、この聖地の対岸には「神が住む島」とも呼ばれる久高島もあります。
訪れる際にはセットでプランに入れるのもおすすめです。
注意したい点として、斎場御嶽を訪れる際にはミニスカールやキャミソールといった肌の露出が多い服装は避けること、ハイヒールなどかかとの高い履物で訪れる際には無料貸出の履物に履き替えることが推奨されることなどがあります。