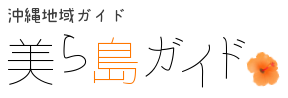シーサーの由来
獅子のことを沖縄ではシーサーと呼び、方言ではしーしーと言います。
シルクロードの時代には、西成ではライオンのことをシと呼んでいたようです。
中国でこのシという音に獅の字を当てて獅子と名付けます。
この時の子には特別な意味はなく、中国では敬称としてよく使われる字であり、日本だと~さんのような感じです。
この獅子という文字が沖縄に伝わり、そしてシーサーやしーしーと沖縄風の発音になっていったのです。
守り神のシーサー
シーサーというと守り神だというのは多くの方が知っている事でしょう。
中国から獅子文化が伝わって500年以上が経っています。
沖縄のシーサーは作者は不明ですが、1470年頃に石で作られた獅子が首里城に設置された記録があります。
この頃はまだ中国の伝統に従って、獅子は王宮の一部の貴族のところにしか設置していませんでした。
首里城時代は冨盛村で火災がしばしば起こり、それに困った人々は風水師に相談すると、近くの八重瀬岳が原因だというので、その山の方角に向けて獅子をおいたら火災は起こらなくなったという記録があります。
このようなことからシーサーは守り神として使われるようになります。
そうして各地で守り神としてシーサーが設置されるようになります。
現在沖縄本島で確認できるこのような守り神として設置されているシーサーは30体ほどです。
昔から数百年も村などを見守ってきたシーサーの姿を今も見ることが出来ます。
最近では沖縄の屋根瓦の上に置かれるシーサーの他に、門柱のある家もありますので、門柱の上に置かれたり、壁に設置したりと、置く場所も変わってきています。
お土産用としてのシーサーも売られています。
門柱の上に設置するなら、シーサーを正面から見て右がオスで左がメスです。
口を開いているのがオスであり、シーサーには性別があるのです。
設置する前にはまずは置く場所を綺麗に掃除します。
そして水洗いして綺麗にした後は、その場所を良く乾燥させましょう。
シーサーを置く場合はボンドで固定しますので、置く場所とボンドの相性を考えて、どのボンドを使用するか決めます。
ボンドを置く場所に付けたらシーサーを固定してボンドが乾燥するまで待ちましょう。
ボンドは1日で乾燥しますが、雨風の強い日はさけて晴れた日に設置した方がいいでしょう。
一度設置してしまえば、沖縄にくる台風でもびくともしませんので、家庭を守ってくれる守り神として長く仕えてくれるでしょう。
門柱の上に置くならやはり背の高い見栄えの良いシーサーがおすすめであり、シーサーは守り神以外に魔除けとしての役割もあります。