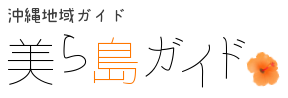琉球漆器とは?
琉球漆器とは、その名の通り沖縄で作られている伝統的な漆器のことで、中国と日本の技術やデザインがミックスされた作りが特徴です。
琉球王朝時代はアジア各国との交流が盛んだったため、さまざまな工芸技術が入ってきましたが、その中に中国の漆器作りがあります。
琉球漆器では、中国で古くから用いられてきた堆朱と呼ばれる漆器作りの技術が採用されているのもそのためです。
とはいえ、琉球漆器は中国だけでなく琉球独自の工夫も凝らされていて、椎錦と呼ばれる加飾技術に発展して現代まで伝わる独特の手法となっています。
漆を何重にも重ねていくことによって装飾を立体的にするもので、より高級感のある雰囲気を作り出すことができます。
琉球漆器にはいろいろな技術が用いられていて、沈金や螺鈿、箔絵などの一般的な漆塗りの技法に加えて、朱色と黒色の漆を組み合わせる花塗などの手法も用いられています。
もともと沖縄は漆が豊富に産出されていて、産出量と共に質の面でも高い評価を受けています。
その漆を用いた漆器の技法が発展していくのは必然だったとも言えるかと思います。
琉球漆器はいくつもの工程を経て完成しますが、やはり特徴的なのはその加飾でしょう。
琉球漆器独自の手法としては堆錦が用いられますが、これは漆と顔料をミックスさせて練り合わせた後、図柄に切り抜いてから器に貼り付けるという方法を取ります。
その上で、さらに着色をしたり細かな線を付けたり、切り取ったりして細部を仕上げていきます。
凝ったものだと複雑な立体形となり、本土の漆器とは異なる立体感のある漆器が完成します。
琉球漆器の歴史について
琉球漆器の始まりは14世紀から15世紀のころだとされています。
琉球王朝では特に中国との交流、貿易に力を入れていましたが、当時すでに中国では卓越した漆器作りの技法が完成されていました。
そこからお手本となる漆器の流入が琉球にもありましたし、職人による技術の習得もなされていました。
その後、琉球王朝の下で貝摺奉行所という組織が設立されます。
これは漆器を王朝の支配下で作るというもので、特に王族を始めとする高貴な人たちが使用したり、宗教儀式で用いたりするための道具を提供するのが目的でした。
こうした歴史があるため、琉球漆器は単なる食事用の道具というだけでなく、儀式用の重要な品としても利用されてきたのです。
琉球漆器は非常に高貴なものでしたので、江戸の時代になって薩摩藩が琉球王国に侵攻すると、琉球漆器を徳川家に献上するといった動きが出てきます。
こうして本土とのつながりが強くなり、漆器作りにも本土の技術が入り込むようになります。
その結果、沈金や螺鈿といった技法を加えた琉球漆器が生まれるようになり、現在のようなさまざまな手法を巧みに使い分ける漆器へと成長していったのです。