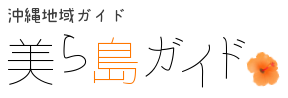琉球ガラスとは
明治時代に大阪や長崎からやってきたガラス職人によって、沖縄にガラス製造の方法が伝えられ、薬瓶やランプなどが作られたのが始まりと言われています。
戦後はコーラやビールの色つきのガラスを再生して、本来なら気泡や厚みのある不良品もデザインとして活かし、そこから沖縄独自のガラスが誕生ます。
そして琉球ガラスは製法や原料を発展させ、平成10年には伝統工芸品に認定されます。
しかしそこで終わったわけではなく、今も琉球ガラスは発展を続けているのです。
琉球ガラスで使用してる原材料は、通常のガラスを作るときと同じように珪砂という砂を原料として、ソーダ灰や石灰を調合します。
そして特徴として製造で出たガラスの破片や断片も原料として再利用します。
これらが窯で焼くと溶けて混ざり合ってガラスになるのです。
ガラスの色は原料を調合する時に、色を出す金属の酸化物を加えます。
それによってガラスに色が付き、琉球ガラスでは基本として青や紫など6種類の色があります。
さらに琉球ガラスの特徴として気泡があることであり、溶けているガラスに重曹を加えて混ぜると無数の気泡が出来、それが光を乱反射してガラスをより美しく見せます。
このような気泡が入ったガラスも琉球ガラスの特徴となっています。
泡は飾りにもワンポイントとしても使われることがあります。
歴史
1600年代には沖縄にガラスが伝わったという記録があるので、このころに琉球ガラスの元となるものが始まったと考えられます。
1730年代になるとガラス職人ではないかと思われる記述も見つかっており、すでにガラス製造の方法が確立されていたと考えられます。
そして明治以降になると、沖縄で大阪などからガラス職人を呼んで、本格的なガラス製造の方法を取り入れます。
しかし沖縄のガラスは、第二次世界大戦中には空襲によって、すべての工房が全焼してしまったために、今は戦前のガラス製品はほとんど残っていません。
戦後まもなく日本に来たアメリカ軍人などがガラス製品を大量に注文するようになったために、コーラやビールの瓶を回収し、それを元にガラス製品を製造し琉球ガラスが復興されます。
その後は琉球ガラスは伝統工芸品として認定されるようになり、琉球ガラス工芸協同組合の設立、新しい着色手法の開発などガラス製造の研究開発、観光品としての売り出しなど、琉球ガラスは発展をしています。
少し前までは観光品としての特色が強かった琉球ガラスですが、工芸品として芸術性を高めるために、工房などで独自の作品を制作するような場所も出てきています。