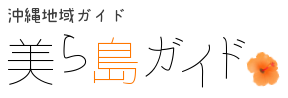楽器や工芸品として
沖縄三味線は楽器としてその音色に魅了される人も多く、沖縄には14世紀頃に伝わったと言います。
三味線の原型となる三絃が元であり、琉球王国では宮廷楽器として使われ、宮廷音楽が出来上がっていきます。
本来は蛇の皮で作られましたが、沖縄では手に入れにくかったので、猫や犬の皮を代わりに使います。
楽器以外にも工芸品としての価値も高く、高価な蛇皮で作った三味線を持っていることは、裕福な象徴にもなります。
三味線愛好家の中には、美しい形状を沖縄の言葉で美人を意味するちゅらかーぎーと形容する人もいます。
また三味線は弾けなくなったとしてもそれを持っていることに意味があるとされた時代もあり、床の間に2つの三味線を夫婦として飾ることは縁起がよいとされます。
三味線の構造
・棹
ソーと呼ばれる部分であり、三味線の音色はこの部分で決まると言われています。
使われる素材は黒檀という黒い木であり、材質は重くて硬く、年月が経過しても反りにくいという特色があります。
ソーと呼ばれる部分であり、三味線の音色はこの部分で決まると言われています。
使われる素材は黒檀という黒い木であり、材質は重くて硬く、年月が経過しても反りにくいという特色があります。
・胴
チーガと呼ばれる部分であり、弦の音を増幅させるところです。
三味線の本体の部分であり、表裏を決めるときは皮の張り具合を見て、音の高い方を表とします。
チーガと呼ばれる部分であり、弦の音を増幅させるところです。
三味線の本体の部分であり、表裏を決めるときは皮の張り具合を見て、音の高い方を表とします。
伝統的な三味線には蛇皮を使うのが一般的ですが、沖縄では戦時中は空き缶を使用したり、傘の記事を使用したものもありました。
蛇皮を使用するときは、天然の蛇皮はワシントン条約に違反するために、現在はニルマニシキなどが使用されます。
また蛇皮以外にも猫や犬の皮が使用されることもあります。
・弦
チルと呼ばれる部分であり、三味線という名の通り弦は3本です。
弦は上から順に、男弦・中弦・女弦と言います。
チルと呼ばれる部分であり、三味線という名の通り弦は3本です。
弦は上から順に、男弦・中弦・女弦と言います。
弦の素材はテトロンかナイロンを使用し、稀にエナメル製もありますが、こちらは手触りが悪いのであまり好まれません。
・糸巻き
カラクイと呼ばれる部部であり、弦を巻いて音色を調節する部品です。
伝統的な形状として首里や埋めや歯車などいくつかのデザインがあり、材料としては黒檀や紫檀が使われます。
カラクイと呼ばれる部部であり、弦を巻いて音色を調節する部品です。
伝統的な形状として首里や埋めや歯車などいくつかのデザインがあり、材料としては黒檀や紫檀が使われます。
また中国の楽器を真似て、象牙やプラスチックで装飾することが多いです。
・爪・撥
ギターのピックにあたる部品です。
演奏するときには、人差し指に装着して演奏し、中には人差し指の爪で直接演奏する人もいます。
ギターのピックにあたる部品です。
演奏するときには、人差し指に装着して演奏し、中には人差し指の爪で直接演奏する人もいます。
そして三味線の形状自体にもいくつか種類があります。
最も古い形の南風原風は細めで小降りなのが特徴であり、久場春殿型は三味線のなかでも最も大型であり、真壁型が最も普及している形などと三味線も7種類の型があります。
もしも弾きたいと思うなら購入して練習することも出来ますが、三味線をレンタルしているようなところもあるので、まずは試しに触れてみるのも良いかもしれません。