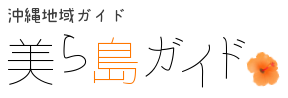沖縄が誇る伝統芸能
「組踊」とは、かつて琉球王朝において宮廷芸能として行われていた音楽・踊りのことです。
沖縄では1429年から1879年の間琉球王朝が存在し、本土とはまた違った歴史を辿っていました。
とくに中国との関係が密接であり、中国からさまざまな文化を導入するとともに、中国からの使者を招いていました。
組踊はそんな中国からの使者を歓迎する際に作られ、実際に行われたものです。
1719年、当時の琉球王朝の王、尚敬王が中国からの使者(冊封使)を招いて冊封儀礼を行う際に実施したのが最初とされています。
当時、踊奉行という地位にいた玉城朝薫(1684-1734)年によって創作されたと言われています。
組踊ってどんな芸能?
このように中国の使者を歓待するために作られた芸能ですが、日本の伝統文化とも非常に密接な関わりがあります。
創作者の玉城朝薫は薩摩藩や江戸など本土に何度か訪れたことがあり、その際に歌舞伎や能楽をはじめとしたさまざまな伝統芸能と接する機会がありました。
そして新しい芸能を作ることになったときに、これらの伝統芸能と琉球に古くから伝わる伝統芸能、さらに中国の演劇(中国戯曲や京劇)を参考にしながら組踊を作り上げていったと言われています。
ですから、現代の日本人がこの組踊を見ると「日本らしい」部分と異国情緒を感じさせる部分の両方を感じます。
どうやら初演の際にも中国からの使者から好評をもって迎えられたらしく、以後宮廷芸能として受け継がけていくことになりました。
創始者の玉城朝薫は「女物狂」「孝行の巻」「銘苅子」「二童敵討」「執心鐘入」の5つの作品を作り、これらを「朝薫の5番」と呼んでいます。
普及と再評価
こうした歴史と経緯から見ても、身分の高い人達の間で行われる宮廷芸能としての面を持っているわけですが、一方ではかなり早い段階から一般人の間でも行われるようになったらしく、19世紀に入る頃には各地の村祭りなどでも上演されていたと考えられています。
それだけ多くの人たちに受け入れられる魅力を持った芸能ということなのでしょう。
これが沖縄だけでなく全国的に知られるようになったのは、戦後、沖縄が日本に復帰した後です。
組踊が沖縄だけでなく日本の優れた芸能として評価されることになり、1972年に国の重要文化財として指定されたのです。
この段階で能楽、歌舞伎、文楽などと同じ評価を得たと言ってもよいでしょう。
さらに2011年にはユネスコの無形文化遺産にも記載され、世界的に見ても価値ある芸能であることが認められました。
現在では「国立劇場おきなわ」などの施設で組踊が上演されており、誰でも鑑賞することができます。
沖縄に訪れた際には、こうした伝統芸能と接する機会を作ってみるのもよいのではないでしょうか。