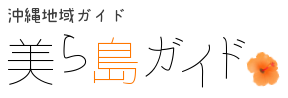沖縄の道に見かける「石敢當」とは?
沖縄の観光スポットを巡る旅も素敵ですが、沖縄の街をのんびりお散歩しながら、民家の赤瓦やシーサーを見たり、のんびりした雰囲気を楽しむ町めぐりを楽しむ方も多くなっています。
沖縄の道には時折「石敢當」と書かれた石碑のようなものが、交差する道路や曲がり角などに設置されています。
石碑のようなものもあれば、交差する道路にある家の塀などに直接「石敢當」と書かれていることもあり、沖縄の民家が立ち並ぶ地域などをお散歩された方はよく見かけたのではないかと思います。
石敢當とは何か?というと、どうやら中国から由来したもので、沖縄本島、周辺諸島、また薩南諸島、奄美などでもよく見かけるといわれており、沖縄、鹿児島以外にもあるようですが、数は少ないといわれています。
いしがんどう、いしがんとうと呼ぶのが沖縄で、鹿児島などではせっかんとうと呼ぶ事が多いといわれているこの「石敢當」は、魔物を除けるためもの、つまり魔よけです。
古くから地域を徘徊する「マジムン」と呼ばれる魔物がいて、この魔物は真っすぐに進むという性質もっているといわれてきました。
T字路、三叉路等に行きあたると真っすぐ進むため、その延長線上にある家の中にマジムンが入ってきてしまうと古くから信じられてきたため、そこに石敢當を設けることで魔物が入れないようにしているといわれています。
石敢當にマジムンが当たると砕け散ってなくなるといわれているため、交差点や曲がり角などに添えつけられている、またこの文字が塀などに書かれているというわけです。
マジムンとは何か?
沖縄、鹿児島県の奄美諸島などに古くから居ついているといわれているのがマジムンです。
このマジムンは悪霊の総称とされており、実は一つの形ではなく様々なマジムンが存在します。
特に動物の姿をしているマジムンが股をくぐるとその人は死んでしまうと言い伝えられており、絶対にマジムンに股をくぐられてはいけないとされてきたのです。
奄美群島などでは「ハブ」をマジムンと呼んでおり、言い伝えによると神様の使いといわれ、このハブは唯一この世に実在される生物のマジムンといわれています。
色々なマジムンがいますが、どれも恐ろしい魔物として言い伝えられてきました。
赤ん坊の死霊といわれるアカングワーマジムンは四つん這いになって人の股をくぐろうと襲ってきます。
動物の姿をしたマジムン同様、股をくぐられた人は死ぬといわれています。
沖縄県読谷村(よみたんそん)では、真っ黒な牛のようなものという牛マジムンが古くから伝わっており、また島尻郡では棺桶を担ぐ装具が姿を牛に変えたと伝えられています。
ブタの姿をしているウワーグワーマジムンは、夜道に現れ人を襲うといわれています。
ちょっと面白いのがミシゲーマジムンで、これはしゃもじ(沖縄の言葉でミンゲーという)の事で、こうした古い食器などがマジムンになるとされているのです。
沖縄はこうした古くから伝えられる魔物などから身を、家を守るために何かをするということが各家庭で行われていますが、有名な物では家を守るシーサーがいます。
日本各地できっとこのような魔物の言い伝えがあると思いますが、沖縄は現在でもこうした言い伝えをしっかりと守っている地域があるのです。