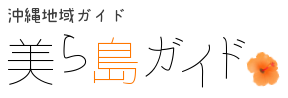ひめゆりの塔とは?
太平洋戦争中、沖縄では激しい戦いが繰り広げられ、多くの犠牲者を出しました。
ひゆめりの塔は、そんな沖縄戦の悲劇を現在につたえる施設としてよく知られています。
この「ひゆめり」とは「ひめゆり学徒隊」のことで、沖縄師範学校女子部と沖縄県立第一高等女学校の生徒とその引率教師によって組織されていた隊です。
女生徒の数222名、引率教師の数18名の、沖縄戦において悲劇的な最期を遂げた彼女たちを慰霊し、戦争の悲惨さを後世に語り継ぐために建てられたのがこの塔なのです。
ですから、塔といっても慰霊碑のようなもので、大きさも高さ数十センチ程度です。
これは建てられたのがアメリカ統治下の1946年だったため、アメリカにはばかったもの、とも言われています。
ひゆめり学徒隊の悲劇
戦況がどんどん不利になっていくなか、沖縄では連日厳しい戦闘が行われていました。
そんななか、負傷兵を看護する要因としてひめゆり学徒隊が組織されたのですが、米軍の圧倒的な戦力の前に負傷者・死者がどんどん増えていく中、彼女たちは看護だけでなくさまざまな役割を担っていたと言われています。
その中には食事の準備や水の確保のほか、戦士した兵士の埋葬も含まれていたと言います。
そんななか、5月には陸軍病院そのものが撤退、地下壕に避難する状況に陥ります。
さらに6月になって突然ひゆめり学徒隊の解散が命じられましたが、完全に米軍が沖縄本島を占領している状況のため、彼女たちは地下壕から脱出できないような状況に置かれていました。
そしてそんな地下壕に米軍が毒ガス攻撃を仕掛け、避難していた学徒隊の多くが命を落としました。
そうした絶望的な状況のなか、自ら命を絶ってしまった者も多かったそうです。
平和の大切さを学ぶ場、そして祈りの場として
このようにひめゆり学徒隊の悲劇を踏まえたうえで、彼女たちの慰霊のため、そして沖縄戦のような飛散な戦争を二度と繰り返さないよう学びの場とするために建立されたのがひゆめりの塔です。
そのため、観光名所としての面があるのは事実ですが、一方で訪れた人たちの多くはこの塔を前にしてひめゆり学徒隊の悲劇的な最期に思いを馳せ、祈りを捧げていきます。
学びの場であるとともに、祈りのための空間とも言えるでしょう。
沖縄戦終結の日とされる毎年6月23日には、慰霊祭も開催されています。
これまで映画や小説などで何度も取り上げられたこともあり、とくに石野径一郎の「ひゆめりの塔」で映画化もされました。
明るく開放的なイメージが魅力の沖縄ですが、過去には戦争による悲劇を味わったこともありました。
こうした歴史を知ることは、沖縄の魅力をさらに深く味わう上でもとても有意義なことになるでしょう。