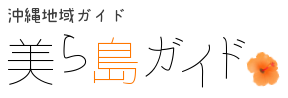沖縄を代表する染め物「紅型」とは
紅型は「びんがた」と読み、正式には「琉球びんがた」という染織物です。
紅型の最大の特徴は、一目見ただけでその華やかさが伝わる白地に鮮やかな色合いで描かれている、花や鳥の様子です。
沖縄らしい花が描かれていますので、本土でよく見る花鳥風月の着物とはかなり違った印象を与えます。
いかにも南国情緒漂う着物といった感じです。
こうした図柄は顔料と植物染料を組み合わせて染めと描きがなされていて、色使いも大胆です。
使われている色は、赤や緑、黄色、青、紫がベースとなっていて、全体的に明るいカラーバランスがとられています。
また、同じ紅型でも、藍型と呼ばれるタイプもあって、こちらは藍色だけで染められていて、その濃淡で図柄を作り出しています。
カラフルな紅型に対して、この藍型はとてもシックで落ち着いた雰囲気を作り出しています。
こちらもやはり沖縄の心を示す、美しい染織物と言えます。
紅型の作り方も2種類存在します。
型紙を使って図柄を描いていく手法と、糊袋という三角形の形をした絞り袋から糊を出して図柄を描いていくという方法があります。
これは筒描きと呼ばれる手法で、職人の技術が求められる高度な作り方です。
といっても、型染めが簡単にできるということではありません。
たくさんの型を使って色を使い分けていくのではなく、紅型では型は一つしか使いません。
そして、糊を型に合わせて塗り付けますが、その後の色塗りは手作業で行います。
沖縄の言葉で「イルクベー」と呼ばれる作業で、独特の彩色の技法が用いられています。
鮮やかな色が使われていますので、ちょっとした筆遣いのミスが大きな失敗につながってしまうこともあります。
それだけに、熟練した職人でないとできない伝統工芸品なのです。
紅型の歴史について
紅型は琉球時代に発達したとされています。
琉球王朝はアジアのさまざまな国との交易を盛んに行っていて、物品そのものの貿易だけでなく文化や技術の行き来もなされていました。
その一つに染色技術や織物技術があり、主に中国などからの技術を取り入れることになります。
琉球独自のセンスや技術を活用して、王族などの身分の高い人たちのための高貴な着物として紅型が発達しました。
こうした琉球王国の庇護によって高度な技術と美しさを持つ染織物に昇華して、現代にまで伝えられるようになったのです。
紅型はその技術と共に、本土にはない独自のデザインも評価されています。
本土の染め物は四季の表現を、春や秋など個別に表現するものです。
しかし、目立った四季のない沖縄の紅型では一枚の着物の中に四季がすべて織り込まれています。
また、中国のデザインをベースにした模様を使いつつも、日本の技術やデザインセンスによって調整されていて、文化の融合を感じることもできます。