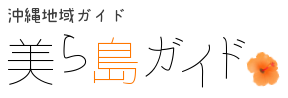沖縄ならではの芭蕉布とは?
沖縄には本土にはないさまざまな特徴的なものがありますが、その一つに芭蕉布があります。
「幻の布」と称される貴重な工芸品で、沖縄の風土だからこそ誕生した織物です。
芭蕉布は主に沖縄県の北部に位置する大宜味村喜如嘉エリアで作られていて、地元ですべての工程を手作業で行っています。
それだけに産出量は極めて少なく、なかなか手に入れることができません。
芭蕉布の原材料は糸芭蕉という植物で、バナナに近い種類です。
この植物から取れる繊維はとても少なく、1反の織物にするためには実に200本もの糸芭蕉を加工しなければなりません。
しかも、上質の繊維を得るには丁寧に糸芭蕉を栽培しないといけないため、芭蕉布の作成は原料となる植物の栽培過程から始まっていると言えます。
糸を撚って紡ぎ糸にしてから、手作業で織っていきます。
完成するまでに実に23もの工程を経る必要があって、長い時間を要します。
また、こうした作業ができる人は年々少なくなっているため、まさに幻の布として稀有な存在となってしまっているのです。
しかし、昔は芭蕉布は重要な織物として沖縄の地で愛用されていました。
最初は王族が身に着ける特別な服で、清王朝や徳川幕府に献上されていたこともありました。
次第に庶民も日常的に着るようになります。
さらっとした着心地で風を通しやすい布であるため、沖縄の高温多湿の気候の中で過ごすのに最適な布だったからです。
芭蕉布は人々の間に浸透して、正装から仕事着までどんなシーンでも着用される服となってきたのです。
芭蕉布がたどってきた歴史
芭蕉布は12世紀から13世紀にはすでに誕生したとされています。
沖縄の地で栽培されていた糸芭蕉を使って、地元の人たちが時間をかけて糸を作り服に仕立てていました。
他に繊維を採れる植物が多くなかったことや、上記のように芭蕉布が沖縄の気候に合っていたということもあって、王族も庶民も利用する一般的な服となっていきます。
この伝統的な織物はずっと引き継がれてきて、昭和の時代になっても芭蕉布を作ることが女性たちの副業となっていました。
自分たちが着用する服を作るだけでなく、沖縄県内のみならず本土でも販売することができるようになったので、家計を助けるための手段となったのです。
しかし、世界大戦によって芭蕉布作りは衰退していくことになります。
多くの人たちが村から出てしまったために、手間のかかる製造工程をすべて行うことができなくなってしまったからです。
しかし、戦後になると芭蕉布の価値を認めた活動家によって、沖縄の伝統的な織物を復活させようとする動きが始まります。
地元で作業できる人を探し再び芭蕉布を作るようになると、その布がさまざまな品評会や工芸展において高く評価されて芭蕉布が世に知られるようになるのです。