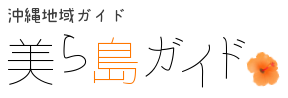太鼓を使った踊りとして
エイサーと聞くと派手な衣装で太鼓を抱えて踊るような人々をイメージするかもしれません。
特に沖縄の観光案内でも度々登場するので、そのようなイメージが強いでしょう。
伝統芸能として昔から行われてきた踊りでもあり、沖縄の青年会がそれぞれの型で踊りながら練り歩きます。
エイサーと一言で言っても色々な型がありますが、現在は大太鼓や締太鼓を中心とした太鼓エイサーが主流であり、沖縄では中部が一番盛んだと言われています。
さらには太鼓を使わない踊りのみのエイサーもあり、今も存在しており、これが最も古い型のエイサーではないかと言われています。
旧盆の踊りとして沖縄では欠かせないエイサーは、先祖送りの踊りとして行われます。
先祖送りの他にも娯楽行事として踊るエイサーもあり、今は沖縄以外でも有名となり、東京などでも年に数回エイサーを披露するイベントなどもあります。
学校の運動会や季節行事に取り入れるところも出てきており、さらには海外までも広がって今やエイサーは様々な面を持つようになっています。
もしもエイサーを見たいというならシーズンとしては7月か8月がピークです。
観光として披露されるエイサーも良いですが、夏場にしか見られないような本場のエイサーもあります。
沖縄では沖縄全島エイサーまつりが開催されますので、それを見に行くのも良いでしょう。
そして各地で太鼓のエイサーの音色が聞こえれば、それは夏の始まりとなります。
エイサーの基本隊列
・大太鼓
エイサーの音頭取りの役割があります。
踊りの間は音がずれないようリードして隊列を導いていく人々であり、とても重要なポジションです。
エイサーの音頭取りの役割があります。
踊りの間は音がずれないようリードして隊列を導いていく人々であり、とても重要なポジションです。
大太鼓を持つ体力も要求され、抱えながら踊りを披露しないとならないので、それもまた難しいポジションになります。
・締太鼓
大太鼓の後ろで踊るのが締太鼓の隊列であり、全体が一糸乱れぬ動きで連携を保って踊ります。
大胆でありながら繊細な踊りを披露しますので、見る人は圧巻されるでしょう。
大太鼓の後ろで踊るのが締太鼓の隊列であり、全体が一糸乱れぬ動きで連携を保って踊ります。
大胆でありながら繊細な踊りを披露しますので、見る人は圧巻されるでしょう。
・男子踊り
手踊りからまず始め、リズムや動きを掴むと太鼓を持って踊ることも出来ます。
足の踏み方などで上達具合がわかるらしく、青年会では空手の型を踊りに取り入れるところもあります。
手踊りからまず始め、リズムや動きを掴むと太鼓を持って踊ることも出来ます。
足の踏み方などで上達具合がわかるらしく、青年会では空手の型を踊りに取り入れるところもあります。
・女子踊り
絣の着物を着てたすきを掛け、足下には草履を履きます。
豆絞りや手ぬぐいを頭に巻くような団体もあり、男踊りは力強いのに対し、女踊りはしなやかで優雅です。
絣の着物を着てたすきを掛け、足下には草履を履きます。
豆絞りや手ぬぐいを頭に巻くような団体もあり、男踊りは力強いのに対し、女踊りはしなやかで優雅です。
・旗頭
隊列の先頭に立って曲のリズムにあわせて旗をテンポ良く振る役割です。
踊りの間に他の青年会と鉢合わせになると、それぞれの旗頭が旗を振って相手の青年会と踊りを競うガーエーと呼ばれる対決のようなシーンが始まります。
隊列の先頭に立って曲のリズムにあわせて旗をテンポ良く振る役割です。
踊りの間に他の青年会と鉢合わせになると、それぞれの旗頭が旗を振って相手の青年会と踊りを競うガーエーと呼ばれる対決のようなシーンが始まります。
このガーエーもエイサーの醍醐味と言えるでしょう。