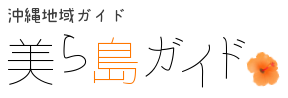八重山諸島で作られるミンサー
沖縄にはいくつかの伝統的な織物があって、その中でもミンサーは高い評価を受けている工芸品です。
ミンサーは沖縄県の中でも八重山諸島で作られていて、主に西表島や石垣島、竹富島などが有名な産地となっています。
八重山諸島には19の大小さまざまな島がありますが、これらの島に生えている植物を使って作られる染料で染めているのが特徴です。
先染めによって色が付いた状態の糸をすべて手作業で織っていき、ざっくりとした風合いの反物に仕上げます。
ミンサーの大きな特徴は、この八重山諸島で取れる天然染料でしか出せない独特の藍色と、五つ玉と四つ玉の模様を組み合わせたシンプルな雰囲気です。
この図柄は「いつの世」とも呼ばれているもので、いつの世になっても愛し合い続けるという想いがこもったデザインなのです。
ミンサーという名前は、沖縄の言葉で「ミン」つまり綿を使って織られている、「サー」つまり幅が狭い反物にしているということを意味しています。
このミンサー帯を使って作られる着物は、紬や一般的な着物、浴衣など幅広い用途で使われていて、夏向けの着物だけでなく一年中使えるのが魅力です。
沖縄の風土に合った布ですので、通気性が良くさらっとした着心地です。
また、丈夫で丁寧に作られているため、長く持つ布で使えば使うほど風合いが良くなるというのも魅力です。
ミンサーのもう一つの魅力は、他の染織物とも違う色合い、そして同じミンサーでも一つ一つ微妙に異なる風合いです。
というのも、染色に使われる植物はいくつもの種類があって、作り手が自ら山で採取して選んでくるからです。
利用する植物の種類とその組み合わせ、染色の時間などによって色の濃さや色味の特徴が異なり、完全オリジナルの染織物ができあがるのです。
ミンサーの歴史について
ミンサーの誕生は17世紀から18世紀のころだと考えられています。
当時の琉球王朝が交易をしていた国は多いですが、中国を経由してチベットやアフガニスタンあたりから、その技術が伝わったと思われます。
細かな記録は残っていませんが、当時すでに綿の製造がなされていたという記録がありますので、ある程度の形がその時代にできあがっていたと考えることができます。
それぞれのエリアで異なるタイプの織物が作られていたようですが、現代に伝わるミンサーのルーツは竹富島と言われています。
この島には「ミンサーフ」という藍色の染織物が伝わっていて、女性が結婚する男性に対して送るという風習がありました。
その染織物には「いつの世」文様が織られていて、末永く一緒にという想いを伝えるために送ったとされています。
こうした島の伝統的な風習に基づく織物が広がって、現在のミンサーに発達していったのです。