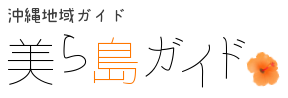ひと味違う?沖縄のぜんざいとは?
そもそもぜんざいとは何かと言うと、「おしるこみたいなやつ」といった認識を持っている方が多いのではないでしょうか。
小豆にお餅や白玉団子を入れた料理/スイーツのことで、汁気が多いものは「おしるこ」、汁気がないものを「ぜんざい」と呼ぶのが一般的です。
そしてこれらぜんざい/おしるこの特徴は「温かいこと」にあります。
おそらく本土の方々は「おしるこが温かいのは当然だろう」と思われるでしょう。
しかし沖縄のぜんざいは違い、冷たいのです。
もともと沖縄では温かいおしるこ/ぜんざいを食べる習慣はあまりなく、ぜんざいといえば冷たいものを指します。
はっきり言ってしまえば、同じ「ぜんざい」と名付けられていますが、本土のぜんざいと沖縄のぜんざいはまったく違う食べ物といってもよいでしょう。
沖縄のぜんざいは甘く似た豆と押し麦、または白玉団子がトッピングされたかき氷のことを言います。
あずきのかき氷を連想してもよいかもしれません。
ただ、使われる豆は金時豆が一般的、かつては緑豆が主流だったと言われています。
現在の沖縄ぜんざいの形が整えられていった経緯も興味深く、もともとは押し麦や豆を入れたお菓子全般を「ぜんざい」と呼んでいたのですが、戦後になって冷蔵庫が普及したことでかき氷に押し麦と豆をトッピングするようになり、やがてこの形が沖縄ぜんざいと呼ばれるようになったのです。
白玉団子がトッピングされるのは、本土のぜんざいの影響なのでしょう。
魅力は?
このように沖縄ぜんざいの基本は「かき氷」ですから、冷たくて爽快感を味わえるのが最大の魅力です。
ひとことで表現すれば、「甘くて冷たくて気持ちいい」でしょう。
何しろ沖縄の夏は暑いですから、暑いなか外出した後や喉が乾いたときにこの沖縄ぜんざいを食べると、体全体の暑さが一気に冷やされるような爽快感を味わうことができます。
ですから、この魅力を存分に味わいたいなら夏に食べること、そしてちょっと暑さを感じてから味わうことがポイントになります。
食べられるスポット
シンプルな料理ですが、使う豆の種類や豆を甘く煮るときの手法によって風味にも違いが出てきます。
沖縄ぜんざいを食べられるスポットで、それらの違いを確かめてみるのも楽しいでしょう。
おすすめスポットとしてはまず沖縄ぜんざいのお店の代表格、老舗でもある「千日(せんにち)」が挙げられます。
伝統的な沖縄ぜんざいをオーダーを受けてから作るスタイルで、根強い人気を得ています。
それからピザ店の「ばーすぬ家」では、「塩黒糖ぜんざい」を食べることができます。
その名前の通り塩と黒糖の風味を活かしているのが特徴で、とくに多良間島産の黒糖の甘みは絶品です。
とてもユニーク、でも本土の人にとってもちょっと懐かしい感じがする、そんな沖縄ぜんざいをぜひ味わってみてください。